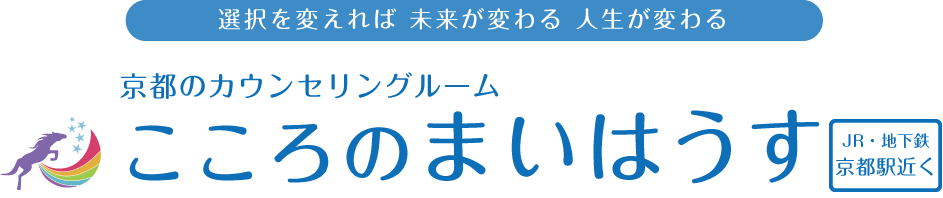ロジャーズの ひとりごと
ロジャーズの ひとりごと · 2025/03/31
「複雑性PTSD」や「心の傷」をテーマにした書籍を紹介します。「複雑性PTSD」は、震災やレイプなどの単回性トラウマによって起こるPTSD〈心的外傷後ストレス障害〉と区別して、2018年に虐待などの反復的な被害による慢性的なトラウマを複雑性PTSDという病として厚生労働省により認定されました。当事者の方、子育て中の方々や、児童福祉や社会福祉の仕事に携わる方々などはもちろんのこと、周りにいる人々、誰の日常生活の周りにも子どもはいるはずです。ひとりでも多くの人に読んでほしいと願っています。
ロジャーズの ひとりごと · 2025/01/31
私のこれまでの人生を支えてきたもののひとつに、人にかけられた言葉があります。また家族から教えられた形見のような、財産のような言葉もあります。そしてそれらの言葉は、私にとても大きな影響を及ぼしています。人からかけられた言葉に救われ、守られてきた気がします。それらの言葉は長々と話された言葉ではなく、ひと言といってもいいくらいです。ある時は何も言われないことで言葉以上の思いが伝わってきたこともあります。逆にかけられたくなかった多くの言葉もありました。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/12/30
「自由死」を選ぶ意志表示をしていた母が、事故で亡くなる前日にひとり息子の朔也に「たいせつな話がある」と言い残し、それが聞けぬままに亡くなった母の本心が知りたくて、ヴァーチャル・フィギュアの作製を依頼するところからストーリーが始まります。『ヴァーチャル・フィギュアには「心はありません」が、学習により「心のようなもの」を感じられることはあります。「身体感覚」はありません』と説明を受けます。ヴァーチャル・フィギュアによって再現された母によって、朔也は自分の知らなかった母を知ることになり、自身の出生について母から聞かされていたこととは違う真実を知ることになります。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/11/30
人は皆、絶対「死」を迎えます。いつか死ぬことを受け入れ、直視して後悔のないように生きようとする覚悟ができた時、より善く生きようとすることができるのだと思います。
「生れてきた意味」は幸せに向かうこと「幸せに向かうには、より善く生きること」と悟るのには随分時間がかかりました。身体の衰えを感じ始めると死ぬことが少しは自然のことと思えるものかもしれませんが、子どもでは自分と死が実感として結びつきにくいです。私の幼少期、学童期の出来事は、子どもだったからこそ、若いからこそ飲み込まれそうな恐怖、不安に囚われてしまったのだと思います。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/10/31
あなたは、これまでの人生で「生れてきた意味」は何だろうか、何か「生れてきた役目」があるのではないかと考えてみたことがありますか?
私は「生れてきた意味」は幸せになること、「生れてきた役目」はないと思っています。
幼少期、学童期の私にとってはとても厳しい出来事から、随分時を経て、現実社会を一所懸命に精いっぱい生きるうちに「死ぬことへの覚悟」と「生き抜くことの覚悟」ができて、そして「生れてきた意味」は幸せに向かうこと、そのために「よりよく生きる」ことだと腑に落ちた時、死の恐怖や不安に囚われていた自分を解放することができました。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/09/30
あなたと相手との関係がうまくいかない原因のひとつは、普段自分では気づいていないあなたの心の奥にある未完の感情です。
未完の感情とは、過去の場面で
ある人へのあなたの感情が出せなかったままだったり
出し切れてなかったり
出したとしても言いくるめられていたり
と、納得いかない状況のまま行き場を失って心に残ってしまった感情です。あなたが感じた強い感情をなかったことにはできません。
多くは親(養育者)との関係で未完の感情が残っています。
未完の感情は、相手が親(養育者)というあなたにとって特別な存在だからこそ、あなたが強く感じた感情です。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/08/31
林真理子さんの著作「小説 8050」を読みました。紹介文には「従順な妻と優秀な娘にめぐまれ、完璧な人生を送っているように見える大澤正樹には秘密がある。有名中学に合格し、医師を目指していたはずの長男の翔太が、七年間も部屋に引きこもったままなのだ。夜中に家中を徘徊する黒い影。次は、窓ガラスでなく自分が壊される――。「引きこもり100万人時代」に必読の絶望と再生の物語。」とあります。(出典 Amazonより) 「小説 8050」には「機能不全家族」「ひきこもり」「いじめ」と取り上げられているテーマがいくつかありますが、読み進めるうちに私はその中で「いじめ」について考えるようになりました。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/07/31
子どもにとっても、段階に応じた適切な境界線(以下バウンダリー)の発達が必要です。
子育ては、乳幼児期の心理的な結びつき「愛着(アタッチメント)」に始まります。
赤ちゃんはお腹がすいた時、おむつが汚れた時など様々な欲求を泣くことで表現します。
「愛着」とは親(養育者)が赤ちゃんの欲求や気持ちを読み取って、世話をすることで育まれる絆のことです。子どもは愛着が形成されることで、自分が安全であると感じるようになります。「愛着」は将来対人関係を築く土台となります。
その次にたいせつなことがバウンダリーです。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/06/30
仕事や結婚で独立して暮らしていたとしても、家族との適切なバウンダリーが引けていないと、罪悪感をもつことなく自分の人生を自由に選択することができません。そのたびに苦しくなったり、落ち込んだり、体調が悪くなってしまうことにもなります。「誰か他の人の為に生きているのではなく、自分の為に生きている」ことは誰しもがわかっていることでありながら、それができていないと思っている人は多いのではないでしょうか。
表向きは自分で選択してきたようにみえても、結果として心の内に罪悪感・不自由が見え隠れしているのであれば、それは自分で選択したことにはなりません。
ロジャーズの ひとりごと · 2024/05/31
今回は、自分の内側の境界線(以下バウンダリー)についてのお話です。
相手との間に引くバウンダリーではなく、自分の内側に引くバウンダリーです。
イギリスの小説家ヴァージニア・ウルフは「時が人の顔つきを変えるように、習慣は人生の容相(様相)を次第に変えていく。そして本人はそのことに気づかない」と日記に記しています。
日々私たちは自分で小さな選択をしながら生活をしています。一日一日の生活の流れを人生とするなら、習慣となる日々のひとつひとつの選択の積み重ねはおろそかにはできないものです。