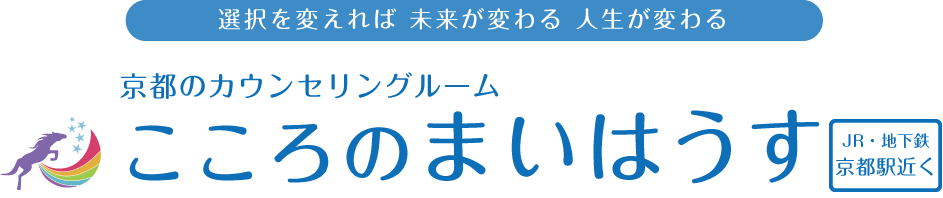「複雑性PTSD」や「心の傷」をテーマにした書籍を紹介します。「複雑性PTSD」は、震災やレイプなどの単回性トラウマによって起こるPTSD〈心的外傷後ストレス障害〉と区別して、2018年に虐待などの反復的な被害による慢性的なトラウマを複雑性PTSDという病として厚生労働省により認定されました。当事者の方、子育て中の方々や、児童福祉や社会福祉の仕事に携わる方々などはもちろんのこと、周りにいる人々、誰の日常生活の周りにも子どもはいるはずです。ひとりでも多くの人に読んでほしいと願っています。


画像Amazonより出典
「わたし、虐待サバイバー」羽馬千恵著
羽馬さんは、五歳くらいまでは祖父母にかわいがられて育った時期があり、『犯罪を実際に犯してしまうか、ギリギリでブレーキがかかるかの違いは、「思い出のなかに振り返る顔があるかないか」だとわたしは思います。その優しい顔がストッパーになるのです。中略ギリギリの怒りを抱えていたわたしを犯罪への欲望から救ってくれたのです。』と書いておられます。子どもたちの周りにいるおとなはそれぞれの立場でなにかできることがあるのかもしれません。
犯罪を犯す、犯さないには生まれ持った性質が大きいと私は思っていますが、虐待を受けて育った方々は、物事の善悪や人にかける思いなど、何を基準に生きればいいのかわからない面があるのではないでしょうか。

画像Amazonより出典
「心の傷と、ともに生きていく」羽馬千恵著
ひとつの例ではありますが、ここまで開示されることは少なく、当事者の方々にとって「心の傷を抱えてどう生きていけばいいのか」を考える参考になるかと思います。羽馬さんは、精神科医療に依存しない回復方法についても記されていますが、17歳から35歳の間に精神科で約15名方に診察を受けられましたが、虐待サバイバーにとって『「特別なトラウマ治療」ができる治療者より、「いつ会っても精神が安定した治療者」の方が、患者の回復にとって重要なポイントだと思います。診療日によって治療者がコロコロと気分で態度がかわりやすい場合は、サレンダー的要素(降伏するという意味で、虐待サバイバーは相手の顔色を常に伺ったり,無理な要求を断り切れないなどの特徴を持つ)をもつ虐待サバイバーにとって、かなりメンタルが不安定になりやすい原因となります(中略)常にメンタルが安定して患者に向き合ってくれる治療者の方が、長期的にみれば患者は回復に向かいやすいと思います。』
特別な訓練を受けてトラウマ治療ができる精神科医を受診する時期と、ある程度回復してきた時期に受診する精神科医とを適切に選ぶことが必要かと思います。

画像Amazonより出典
「ルポ虐待サバイバー」植原亮太著
福祉の現場で著者が体験された事例がたくさん書かれた著書ですが、その中でたくさんの当事者の叫び声が浮かびあがってきます。著者の深い洞察力と感性は見事です。話を聴く側には本来持っている性質と、経験を重ねていく中で培われるものとがあると思います。植原さんは「ここでこうやって話していると親のことを愛せと言われているような気がして、つらい」と言ってカウンセリングに来なくなったある女性のことをきっかけに、カウンセリングの中で自分の解釈や分析を伝えることを慎むようになったと言います。『結局は、私自身の価値観や人生観から導き出されているに過ぎないからである』そして『私たちも彼ら被虐待者も、悩みの根っこをたどると親との問題に行き着くのは必然である。しかし、「親がいる」から生じる悩みと、「親がいない」から生じる悩みとでは、そこにいたるまでの過程も質もことなっている。当然「親がいない」ことによる悩みを「親がいる」人が理解していくことは難しい。これが私が本書で主に伝えたいことだった』と記されています。
誰ひとりとして同じ人はいないですし、その人生もどれひとつとして同じ人生もありません。生れた環境も違いますし、持って生まれたものもひとりひとり違います。自分のことも、人生で起きる出来事も、やがて向き合い受け入れていくことでしか人生を前に進めることができないのかもしれません。まず聴く人がいること、そして聴く人は、相手の状況をわかろうとして聴くこと、相手を理解しようとして聴くことがとてもたいせつなことだとあらためて思います。

画像Amazonより出典
「トラウマ「こころの傷」をどう癒すか」杉山登志郎著
発達障害、複雑性PTSDの第一人者が治療についてわかりやすく解説されています。
こちらも当事者の方々や周りの方々の参考になればと紹介しておきます。
〈注〉文中『 』で括った文章は、書籍本文より引用。
虐待から子どもを守るのがいちばんたいせつなのは言うまでもありませんが、複雑性PTSDを病というのならばなおのこと、子ども時代だけではなく、成人してからの困難にも、生活面や精神面を社会福祉などワンストップで支えていく必要があります。表には見えにくい困難も理解される社会に成熟していく必要があると思います。それにはひとりひとりの意識改革が必須です。今、ひとりひとりができること、それは知ること、理解しようとすることなのではないでしょうか。